生成AIが学習を阻害する|Wharton研究が示す「松葉杖効果」の実証
生成AIが学習を阻害する|Wharton研究が示す「松葉杖効果」の実証
更新日:2025年10月17日
📄 論文情報
- タイトル:Generative AI without guardrails can harm learning: Evidence from high school mathematics
- 著者:Hamsa Bastani, Osbert Bastani, Alp Sungu, Haosen Ge, Özge Kabakcı, Rei Mariman
- 機関:University of Pennsylvania (Wharton School, Engineering School), Budapest British International School
- 発表:2024年7月(SSRN)、2025年6月(PNAS掲載)
- 論文URL:https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4895486
- カテゴリー:認知心理学×AI、人間とAIの共生
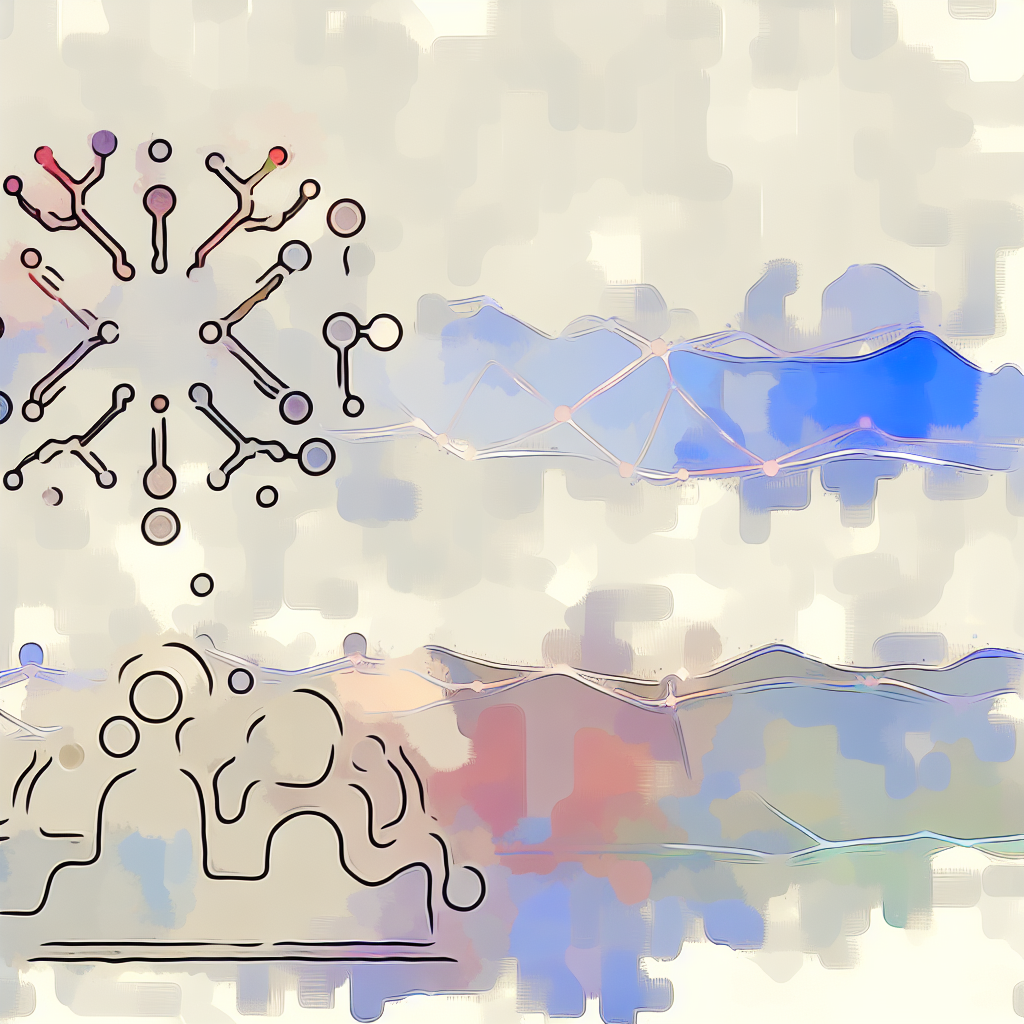
第1章:研究の背景と問題意識
生成AIのパラドックス
生成AI、特にChatGPTやGPT-4のような大規模言語モデル(LLM)は、人間の生産性を大幅に向上させることが示されています。しかし、重要な疑問が残されていました:生成AIは人間の学習、すなわち新しいスキルを習得する能力にどのような影響を与えるのか?
この問いは、単なる理論的関心にとどまりません。特に、AIが誤りを犯す可能性がある領域では、人間の専門家がその出力を確認する必要があります。もし生成AIの使用によって人間のスキル習得が阻害されるならば、長期的な生産性の向上は望めません。
なぜ数学教育なのか
研究チームは、トルコの高校における数学クラスを実験の場として選びました。数学は以下の理由から理想的な研究対象です:
- 明確な正解が存在する:学習効果を客観的に測定できる
- スキルの積み重ねが重要:基礎が身についていないと応用問題が解けない
- 即座のフィードバックが可能:練習問題とテストで学習効果を測定
- AIの誤答が検証可能:生徒がAIの出力を確認する必要性
この研究は、教育現場における生成AI導入の是非を問うものではありません。むしろ、どのように導入すれば学習効果を最大化できるかを明らかにすることが目的です。
第2章:実験デザインと結果
実験の設計
研究チームは、約1000人の9年生、10年生、11年生を対象に、大規模なランダム化比較試験(RCT)を実施しました。
3つのグループ
| グループ | 使用ツール | 特徴 |
|---|---|---|
| 統制群 | なし | 教科書とノートのみ使用 |
| GPT Base群 | GPT-4(標準版) | ChatGPT-4と同様のインターフェース、直接的な回答を提供 |
| GPT Tutor群 | GPT-4(ガードレール付き) | 直接的な回答を避け、段階的なヒントを提供 |
セッションの流れ
各グループは4回の90分セッションを受けました。各セッションは以下の3部構成:
- 教師によるレビュー(約30分):新しい概念の説明
- 補助付き練習時間(約30分):各グループが割り当てられたツールを使用
- 補助なし試験(30分):AIなしで問題を解く
驚くべき結果
練習時のパフォーマンス向上
補助付き練習時間では、AI使用グループが圧倒的な成績向上を示しました:
- GPT Base群:統制群と比較して+48%のパフォーマンス向上
- GPT Tutor群:統制群と比較して+127%のパフォーマンス向上
ここでの「+48%」「+127%」は、正答数や得点の相対的な増加率を示します。例えば、統制群の平均正答数が10問の場合、GPT Base群は14.8問、GPT Tutor群は22.7問正解したことを意味します。
補助なし試験での衝撃的な結果
しかし、AIを使わずに行った試験では、状況が一変しました:
- GPT Base群:統制群と比較して-17%のパフォーマンス低下
- GPT Tutor群:統制群とほぼ同等のパフォーマンス
「生成AIへのアクセスは、教育成果を損なう可能性がある。」
— Bastani et al. (2024)
「松葉杖効果」の発見
研究チームは、この現象を「松葉杖効果」(Crutch Effect)と名付けました。生徒たちは練習時にAIを「松葉杖」として使用し、問題を自分で考えずにAIに頼ってしまったのです。
さらに興味深いことに、GPT Baseを使用した生徒たちは、自分の能力を過大評価する傾向が見られました。練習時の高いパフォーマンスが、実際のスキル習得と誤認されたのです。
GPT Tutorのガードレール(段階的なヒント、直接的な回答を避ける設計)が、この「松葉杖効果」を大幅に軽減しました。これは、AIの設計次第で学習効果を守ることが可能であることを示しています。
統計的信頼性
この研究は大規模なRCT(ランダム化比較試験)であり、結果の統計的信頼性は非常に高いと評価されています:
- サンプルサイズ:約1000人(3学年にわたる)
- ランダム割り当て:生徒を無作為に3グループに分割
- p値 < 0.05:統計的に有意な差が確認された
p値は、帰無仮説(この場合は「AI使用が学習成果に影響しない」)が正しいと仮定したときに、観測された結果と同程度かそれ以上に極端な結果が得られる確率を表します。p < 0.05 であれば、「AI使用の影響がない」という仮説のもとでは今回の差は滅多に起こらず、実際にAI使用が影響していると判断できます。
第3章:認知心理学的考察と今後の展望
なぜ学習が阻害されるのか
この研究結果は、認知心理学の複数の理論と一致します:
1. 望ましい困難(Desirable Difficulties)
心理学者Robert BjorkとElizabeth Bjorkが提唱した「望ましい困難」理論によれば、学習時にある程度の困難や苦労がある方が、長期的な記憶定着と理解が深まるとされています。
GPT Baseを使用した生徒は、練習時に困難を回避できたため、深い理解に至らなかったと考えられます。
2. メタ認知の誤判断
生徒たちは、練習時の高いパフォーマンスを「自分の能力が向上した」と誤解しました。これはメタ認知(自分の認知プロセスを認識する能力)の失敗です。
AIの支援により簡単に正解を得られたため、「理解している」という錯覚に陥ったのです。
3. 認知的負荷の外部化
問題解決に必要な認知的負荷(考える負担)をAIに外部化することで、脳内の問題解決プロセスが活性化されませんでした。これは、筋肉を使わなければ筋力が低下するのと同じ原理です。
ガードレールの重要性
GPT Tutorがなぜ効果的だったのかを理解することは、今後のAI設計に重要です:
GPT Tutorの設計原則
- 段階的ヒント:直接的な答えを与えず、考えるための手がかりを提供
- ソクラテス式対話:質問を通じて生徒自身に答えを導かせる
- 教師の知見を組み込み:教育学的に適切な支援方法を実装
- 生徒の思考プロセスを尊重:即座の正解よりも理解のプロセスを重視
教育現場への実践的提言
- AIを「アシスタント」として位置づける:完全な代替ではなく、学習を支援する道具として
- 段階的な導入:基礎スキルが身についてからAIを使用
- 定期的なAIなし評価:真のスキル習得を確認
- メタ認知の訓練:自分の理解度を正しく評価する能力を育成
- 批判的思考の重視:AIの出力を鵜呑みにせず、検証する習慣
認知科学からの示唆
この研究は、人間の学習メカニズムとAIの関係について、重要な示唆を提供します:
「私たちは、AIを『仕事を簡単にする道具』ではなく、『スキル習得を支援する道具』として再定義する必要があります。短期的な生産性向上と長期的なスキル習得のバランスを、慎重に設計しなければなりません。」
— 研究チームの提言
批判的検討
この研究に対しては、いくつかの批判や追加検討が必要な点も指摘されています:
考慮すべき交絡因子
- 生徒の数学基礎能力:実験前の能力差が結果に影響した可能性
- 学習動機:AIを使うこと自体がモチベーションに影響
- 教師の質:教師の指導方法がグループ間で異なった可能性
- 外部支援:家庭での学習環境の違い
- 技術慣れ:AIツールへの慣れの程度
これらの要因を統制するため、今後の研究では多変量回帰モデルや追跡調査が提案されています。
今後の展望
1. AI設計への影響
この研究結果は、教育用AIの設計に大きな影響を与えています。すでに、Khan AcademyのKhanmigoなど、ガードレール付きAIチューターの開発が進んでいます。
2. 職場への応用
教育だけでなく、職場でのAI導入にも重要な示唆があります。新人社員が生成AIに過度に依存すると、基礎的なスキル習得が阻害される可能性があります。
3. 政策への影響
2024年の国連Global Digital Compactでは、AI安全性に関する国際科学パネルの設立が提案されました。このような研究は、教育政策におけるAI規制の科学的根拠となります。
4. 長期的影響の研究
今後必要なのは、数ヶ月〜数年にわたる長期的な追跡調査です。短期的な学習阻害が、長期的にどのような影響を及ぼすのかを明らかにする必要があります。
学習ポイント:研究手法から学べること
- RCTの重要性:因果関係を明確にするための無作為割り当て
- 統制群の設定:比較対象を明確にする
- 多面的評価:練習時と試験時の両方で評価
- 大規模サンプル:約1000人で統計的信頼性を確保
- 現実的設定:実際の教育現場で実験を実施
1. Bastani, H., Bastani, O., Sungu, A., Ge, H., Kabakcı, Ö., & Mariman, R. (2024). Generative AI Can Harm Learning. SSRN. https://ssrn.com/abstract=4895486
2. Bastani, H., et al. (2025). Generative AI without guardrails can harm learning: Evidence from high school mathematics. Proceedings of the National Academy of Sciences, 122(26), e2422633122.
3. Bjork, R. A., & Bjork, E. L. (1992). A new theory of disuse and an old theory of stimulus fluctuation. In A. Healy, S. Kosslyn, & R. Shiffrin (Eds.), From learning processes to cognitive processes: Essays in honor of William K. Estes (Vol. 2, pp. 35–67). Erlbaum.
4. Wharton School. (2024). Without Guardrails, Generative AI Can Harm Education. Knowledge at Wharton. https://knowledge.wharton.upenn.edu/article/without-guardrails-generative-ai-can-harm-education/
本記事は2025年10月17日時点の情報に基づいて作成されています。AI技術は急速に進展しており、本記事の内容が将来的に変化する可能性があります。教育現場でのAI導入については、最新の研究成果を参考にし、専門家の助言を求めることをお勧めします。
他の記事を見る(4件)
- Transformerの注意機構|人間の選択的注意から学ぶAI設計
- 生成AIが学習を阻害する|Wharton研究が示す「松葉杖効果」の実証
- 人間の学習メカニズムを数理で解明|MIT認知科学が示す少数事例学習の秘密
- SNSマーケティング数理モデル考察|最新研究で検証された拡散理論と実践戦略




コメント (2)